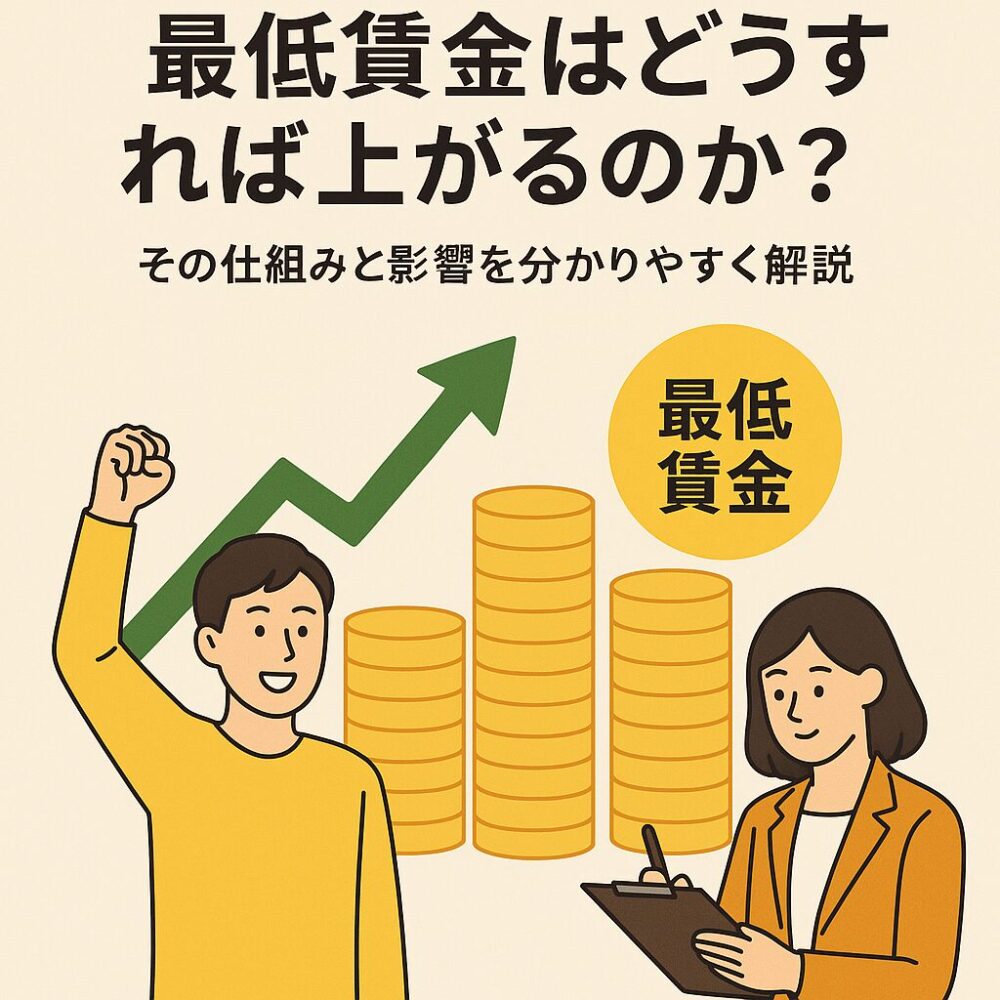最低賃金はどうすれば上がるのか?その仕組みと影響を分かりやすく解説
最低賃金の引き上げは、私たちの生活に直接かかわる重要なテーマです。
しかし、「なぜ最低賃金は上がるのか」「どうすればもっと上がるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、最低賃金が上がる仕組みと社会全体でどのような働きかけがなされているのかをわかりやすく解説していきます。
最低賃金とは何か?
最低賃金とは、法律で定められた「労働者が最低限受け取るべき賃金」のことです。
企業がこれを下回る時給で働かせることは違法であり罰則の対象となります。
日本では「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、主に都道府県ごとに異なる水準で設定されています。
最低賃金の目的は、労働者の生活の安定と雇用の安定を図ることです。
つまり、働く人が一定の生活を維持できるようにすることが主な狙いです。
最低賃金は誰が決めているのか?
日本の最低賃金は、「中央最低賃金審議会」という厚生労働省の審議会によって、毎年議論・答申されます。
この審議会は、労働者側(労働組合など)、使用者側(経済団体など)、そして公益代表(学者や弁護士など)の三者構成で成り立っており、バランスの取れた意見交換が行われます。
審議会では、景気や物価の動向、企業の支払い能力、生活保護との整合性などを考慮して、最低賃金の「目安額」を決定します。
その後、各都道府県ごとの地方最低賃金審議会で、地域の実情に応じた具体的な金額が決まるのです。
最低賃金が上がる要因とは?
最低賃金が上がる背景には、いくつかの主な要因があります。
1. 経済成長と物価上昇
経済が成長し、物価が上昇すれば、それに伴って生活費も増加します。
生活に必要なコストが上がれば、それを補う形で最低賃金の引き上げが必要となります。
2. 労働力不足
近年では少子高齢化により、働き手の数が減少しています。
人材確保のために賃金を上げざるを得ない企業が増えており、これが全体の賃金上昇と最低賃金の引き上げにつながっています。
3. 政治的な意志
政府が「格差是正」や「働き方改革」を進める中で、最低賃金を段階的に引き上げる方針を掲げていることも大きな要因です。
特に「全国平均で時給1,000円以上にする」といった具体的な目標が掲げられると、審議会でもその実現に向けて議論が進みます。
最低賃金を上げるためにできること
最低賃金を引き上げるには、国の政策や審議会だけでなく、社会全体の声や行動が影響を与えます。
以下のような取り組みが効果的です。
1. 労働組合や市民団体の活動
労働組合や市民団体が最低賃金引き上げを求める運動を行うことで、審議会や政府に対する強い働きかけとなります。
署名活動やデモなどの「声」は、政策決定に大きな影響を及ぼします。
2. 選挙での意思表示
最低賃金の引き上げを重視する候補者や政党を支持することも、重要な意思表示の手段です。
政治家は有権者の声に敏感であり、選挙での支持が政策に反映されやすくなります。
3. 企業の理解と協力
企業側の姿勢も重要です。
一部の企業では、法定以上の時給を自ら設定する「リビングウェイジ(生活賃金)」の導入が進んでいます。
こうした取り組みが広がることで、最低賃金引き上げへの社会的合意が形成されやすくなります。
最低賃金が上がると起こる変化
最低賃金が上がると、働く人々の生活が安定する一方で、企業側には賃金コストの増加という課題も生じます。
メリット:
-
生活の質の向上
-
消費の活性化(所得が増えれば消費も増える)
-
雇用の安定や意欲の向上
デメリット:
-
中小企業の経営負担
-
雇用調整(非正規のシフト削減など)の可能性
-
地域間格差の拡大(特に地方では負担が重くなる場合も)
これらをどうバランスさせるかが、最低賃金政策の課題です。
まとめ:最低賃金は「みんなの力」で上がっていく
最低賃金は自然に上がるものではなく経済状況や政策、そして社会の声に基づいて決まります。
「自分には関係ない」と思わずに、日頃から労働条件に関心を持ち、選挙や社会活動に参加することが、最低賃金引き上げへの一歩につながります。
未来の働き方や生活をより良いものにするために、最低賃金の動向に注目し私たち一人ひとりができる行動を考えていきましょう。