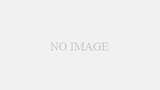|
|
はじめに
「紙ストローになって飲みにくい」「プラスチックに戻った?」など、マクドナルドのストロー素材についてSNS等で話題になることが増えております。
実際に、紙ストロー導入からその後の見直し・廃止検討まで、「なぜそうなったのか?」という疑問も多く聞かれます。
今回はその事情を読み解き、働くビジネスパーソンの皆様にも理解しておいて頂きたいポイントを整理いたしました。
紙ストロー導入の背景:脱プラスチックの潮流
まず、マクドナルドが紙ストローを導入した背景には、企業としての環境対応・脱プラスチックの取り組みがございます。
-
日本マクドナルドは、公式に「2025年末までに、お客様提供用容器包装類を、再生可能な素材、リサイクル素材または認証された素材に変更します」との目標を掲げています。
-
その一環として、2022年10月より紙ストロー・木製カトラリーの提供を開始しています。
-
紙や木材は、FSC®認証材(森林認証)など環境配慮された原料が用いられており、プラスチック使用量の削減効果が見込まれていました(例えば年間約900トン削減を見込むという報道もあります)
つまり、ストローを紙製に切り替えることは「使い捨てプラスチック削減」「資源循環型社会への貢献」という大きな枠組みにおける戦略的な一手でした。
紙ストロー見直し・廃止検討の理由
では、なぜ「紙ストローを廃止または見直す」という報道・動きが出てきたのでしょうか。
主な理由を整理いたします。
1.利用者からの“飲みにくさ”や“味・使用感”の指摘
紙ストロー導入後、消費者から以下のような声が多く上がりました。
-
「紙ストローだと飲みにくい」あるいは「プラスチックの時の方が飲みやすかった」
-
「時間が経つとふやける・曲がる」など耐久性・機能性に対する不満。
-
「紙の質感・においが飲み物の味に影響する」など、飲む際の満足度に関わる評価。
このような「使い勝手」に関する声が一定量あったため、紙ストロー運用における“利用者満足”とのバランスが課題になっておりました。
2.店舗運用・素材在庫・導入負荷
-
紙ストローへ切り替える際には、素材の仕様検討、安全・耐久性・風味保護などが課題としてあげられています。
-
また、SNS上では「紙ストロー在庫が切れてプラスチックストローが出された」といった報告もあり、店舗ごとの運用負荷・素材安定供給が影響している可能性があります。
こういった“導入後の運用コスト・現場課題”も、見直しを検討する要因と考えられます。
3.さらなる“次のステップ”素材・形態の検討
紙ストローの導入は「まずプラスチックから紙へ」という明快な切り替えでしたが、環境戦略としては「紙だけ」では終わらず、更に進化した素材・形態を検討する動きがあります。
-
例えば、紙ストローの先を“ストローなしで飲める蓋(ストローレスリッド)”という形に変更し、ストロー自体を省くテストが一部店舗で実施されていることが報じられています。
-
また、紙・木材だけでなく「バイオマスプラスチック」、「リサイクルPET」など次世代のサステナブル素材にも移行を進めている旨、公式で‐記載があります。
つまり「紙ストローの廃止・見直し」には、“紙で終わりではない”という業界の進化も背景にあるのです。

紙ストロー廃止ではない:誤解を正す
「紙ストロー廃止」との見出しも出ていますが、注意すべき点があります。
-
全国店舗で「紙ストローを完全廃止」したという公式発表は確認されておりません。
-
マクドナルド公式でも「2022年10月より紙ストロー・木製カトラリーの提供を開始」などの記載はありますが、紙ストロー終了の明記はありません。
-
在庫状況・店舗オペレーション等によりプラスチックストローやストローなしの形態が出ているケースが“テスト的に”存在するという報道です。
したがって、「紙ストロー廃止=全面撤廃」と捉えるのは早計と言えます。利用者からの要望や在庫状況によって、例外的にプラストロー提供も継続されているようです。
働くプロフェッショナルとして知っておくべきポイント
-
企業のESG/サステナビリティ戦略の一環として位置づけられる:紙ストロー導入・見直しは、環境(Environment)という観点での取り組み。ビジネスパーソンとして、こうした“生活の中に関わる企業の環境戦略”に目を向けることは、社会・市場の動き理解に資します。
-
“使いやすさ”と“環境配慮”のバランスが重要:環境配慮が目的であっても、利用者の体験を大きく損なうと定着しません。飲食サービスにおける“操作・飲みやすさ”という小さな要素がブランド体験に影響を与えます。
-
変化は段階的・テスト的に進む:新素材や新方式(ストローレスリッドなど)は、一部店舗での試験導入という形で進められており、即時全国展開とは限りません。この“段階導入”を理解することが、組織・チームで制度変更を進める際のヒントになります。
-
コミュニケーションが鍵:利用者にとって急な変化は戸惑いや不満を生みます。企業が「地球環境のために ご理解を」とメッセージを出している点も重要です。ビジネス上でも、変化を伴う施策では関係者・顧客への説明・対話が不可欠です。
まとめ:なぜ「紙ストローから廃止・見直し」なのか
まとめますと、マクドナルドが紙ストローを導入し、その後“廃止または見直し”という動きにつながった背景は次の通りです:
-
プラスチックごみ削減という社会的要請・企業責任から紙ストロー導入。
-
しかし、飲み口の使い勝手・在庫運用・素材特性など利用者・店舗双方にとっての課題が表出。
-
そのため、次のフェーズとして“ストローなし”“バイオマス素材”“リサイクル素材”などより進んだ選択肢を検討。
-
ただし、完全な紙ストロー廃止というわけではなく、あくまで段階的な試行・運用見直しという位置づけである。
このように、「紙ストロー=環境対応」のみに留まらず、「使いやすさ」「運用コスト」「次世代素材への準備」といった複合的視点で変化が起きています。
終わりに
働く皆様が日常的に利用する店舗で起きているこうした“素材・サービスの変化”にも、企業の戦略や社会の流れが反映されています。
マクドナルドのストロー素材変更は、その典型例と言えるでしょう。
ブログや社内報、資料作成時にも「環境対応=良いこと」という単純な論点だけでなく、「使う人の体験」「運用実態」「次のステップ」がどう考えられているかを押さえておくと、より深く読み解くことができます。
|
|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4db47f07.3abf07da.4db47f08.92aea9c6/?me_id=1423662&item_id=10000020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fiernas%2Fcabinet%2F10435155%2F11501092%2Fcompass1753945970.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d50f745.011a69ec.4d50f746.c7e898ce/?me_id=1224379&item_id=10034443&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2F11667147%2F10%2F12564690%2F2536-main-251016.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)