|
|
【千葉と伊豆大島で急増】キョン大量繁殖の理由と最新対策とは
小型シカ「キョン」とは?
「キョン(英名:Muntjac)」は、中国南部や台湾原産のシカ科の小型哺乳類です。
体長約1mと小柄ながら繁殖力が強く、近年日本でも野生化が進み、千葉県の房総半島や東京都・伊豆大島で大量繁殖しています。
本来は動物園や観賞用に輸入されたものが逃げ出したことがきっかけとされ、今では農作物への被害や生態系への影響が深刻化しています。
キョンが大量繁殖している主な理由
① 天敵がいない環境
房総半島や伊豆大島には、原産地に生息するヒョウやオオカミといった天敵が存在せず、自然に個体数を抑える要因がほとんどないことが大きな要因です。
その結果、捕獲しない限り個体数が増え続ける構図となっています。
② 高い繁殖力
メスのキョンは生後半年ほどで妊娠可能となり、出産後すぐに次の妊娠ができる場合もあります。
年間を通して繁殖できるため、短期間で爆発的に数を増やすのです。
たとえば、2006年度に千葉県内で約1万頭だった推定生息数は、2022年度には約7万頭以上にまで増加しました。
③ 適した気候と豊富な食物
温暖な気候の房総半島南部や伊豆大島は、キョンが生息するには理想的な環境です。
竹林や里山が多く、隠れ場所やエサが豊富なため、定着・繁殖に拍車をかけています。
千葉県での被害と現状
千葉県では、キョンによる農作物被害が拡大しています。
県資料によると、年間数千万円〜数億円規模の損失が報告されており、キャベツやサツマイモ、果樹などが食い荒らされています。
生息地域は「君津市」「鴨川市」「大多喜町」「富津市」「いすみ市」など房総南部に集中していますが、北上傾向も確認されており、県全体に拡大しつつあります。
 |
価格:4980円 |
![]()
千葉県の防除対策と支援制度
千葉県では、「第2次キョン防除実施計画(令和3~8年度)」を策定し、分布拡大防止と個体数削減を目指しています。
捕獲には「くくり罠」や「箱罠」が多用され、令和5年度の捕獲頭数は約1万頭に達しました。
また、市町村ごとに「防護柵設置補助金」や「有害鳥獣捕獲協力隊」などの地域支援体制を整備。
住民も参加できる防除活動が進められています。
ただし、繁殖スピードに対して捕獲が追いつかず、依然として個体数は増加傾向です。
伊豆大島でのキョン対策の特徴
伊豆大島では、人口約7,000人に対し、キョンの数が人口の2倍以上といわれるほどの異常繁殖が発生しています。
島特有の生態系に深刻な被害をもたらし、希少な植物が食害を受けるケースも。
このため、東京都と島民が一体となり、
-
捕獲報奨金制度(1頭あたり8,000円)
-
金網柵の大規模設置
-
住民・猟友会・行政の共同捕獲
など、全国的にも珍しい報奨金制度と住民参加型の取り組みが行われています。
これにより、2018年以降は生息数がやや減少または横ばいになったと報告されています。

問題解決に向けた今後の課題
千葉・伊豆大島ともに、捕獲頭数は増えているものの、依然として個体数増加のスピードが速く、根本的な解決には至っていません。
専門家は「捕獲だけでは限界がある」と指摘しており、地域住民・自治体・研究機関が連携し、
-
捕獲効率の向上
-
繁殖抑制技術の導入
-
生息環境の改善
などの総合的対策が求められています。
まとめ:共存のための現実的アプローチを
キョンの大量繁殖は、単なる動物問題ではなく、人間社会と自然のバランスの問題でもあります。
千葉や伊豆大島のように、地域全体で防除・協力体制を築くことが、今後の鍵となるでしょう。
もし自分の住む地域で目撃情報があれば、放置せずに自治体へ報告し、地域ぐるみでの対策に参加することが大切です。
|
|
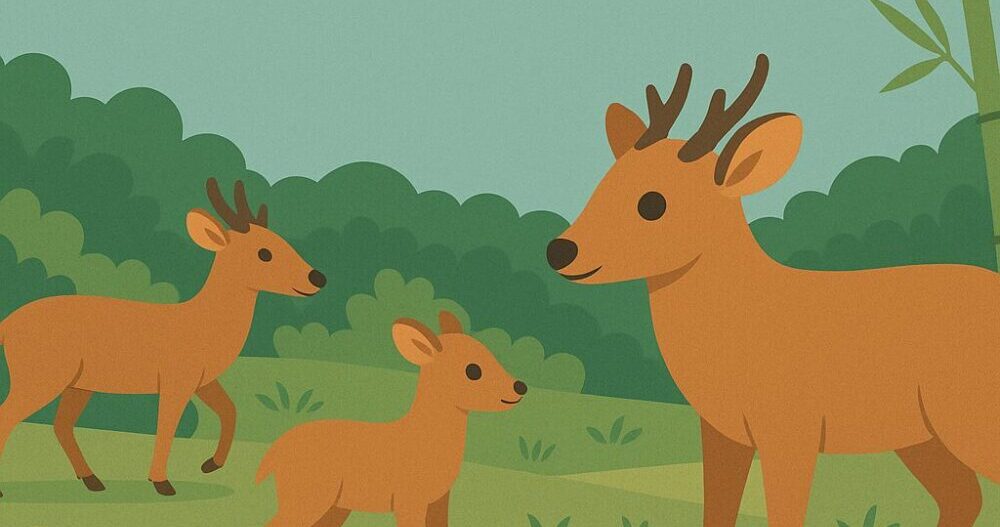
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e0485ae.a0b21f3c.4e0485b0.ee1f1021/?me_id=1374936&item_id=10000342&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftokusenkan%2Fcabinet%2Faut%2Faut-00%2Faut-009_rt12a.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


