|
|
ノーベル化学賞受賞の快挙 — 選考と受賞理由
2025年10月8日、京都大学の理事・副学長であり、高等研究院特別教授の北川進氏が、金属有機構造体(MOF, PCP 等)の研究により、ノーベル化学賞を受賞したことが発表されました。
受賞対象とされたのは、「多孔性金属錯体」の開発であり、北川氏はリチャード・ロブソン(Richard Robson)氏、オマー・ヤギー(Omar M. Yaghi)氏とともに選ばれました。
この発表は、日本の化学界、そして材料化学を志す多くの若手研究者たちに、大きな刺激を与えるものとなりました。
来歴と学術的背景
北川進氏は1951年7月4日、京都市下京区出身。
京都大学工学部石油化学科を1974年に卒業し、1979年には同大学で博士号を取得しました。
卒業後は近畿大学に助手として着任。
その後、講師、助教授を経て、1992年に東京都立大学(無機化学)教授、1998年には京都大学大学院工学研究科で教授に就任しました。
2007年には、京都大学に「物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)」が設立され、北川氏は副拠点長を兼務、2013年からは拠点長を務めました。
また、学外でも国際的な共同研究ネットワークを持ち、客員研究者としてアメリカ・テキサス州立大学(Texas A&M)などとも交流を行っています。
これまでに受賞してきた学会賞・栄誉も多く、洪堡研究賞、紫綬褒章、日本学士院賞、さらには英国王立協会の外国人会員選出など、多彩な栄誉を重ねてきました。
研究の核心 — 多孔性金属錯体(MOF/PCP)の世界
北川氏の受賞に至った研究テーマのキーワードは「多孔性金属錯体(Metal-Organic Framework, MOF)および配位性高分子錯体(PCP)」。
配位化学と「空間」を操る発想
従来、金属錯体(配位化合物)は比較的密な結晶構造をとることが普通でした。
しかし北川氏は、配位化学構造の中に“空隙(すき間)”を導入し、その空隙を機能的に制御するという発想を進め、「配位化合物にも“多孔性”という概念を導入できる」ことを示しました。
この発想こそが、MOF/PCP が「ガスの吸着・分離・貯蔵」「分子識別」「触媒作用」などを行える画期的材料となる土台となったのです。
ソフトクリスタルという新潮流
さらに北川氏は、これら多孔性材料が硬い結晶性構造ばかりではなく、外部刺激(温度変化、圧力変化、化学物質の侵入など)に応じて構造を変化させうる「ソフト構造」も併せ持つことを予見し、実証してきました。
たとえば、ガス分子が侵入したときに孔構造が広がったり、閉じたりする“応答性ナノポア”の制御は、新しいタイプのセンサー材料や選択的吸着材への応用展開を可能にします。
こうした機能性調整と制御性を併せ持った“化学空間(coordination space)”の操作という視点は、北川氏の研究哲学そのものとも言われています。
研究の意義と社会的インパクト
エネルギー・環境分野への応用期待
多孔性金属錯体は、非常に軽量で高い比表面積を持つ構造を実現できるため、水素やメタンなどのガス貯蔵材料として注目されています。
また、特定のガスを選択的に吸着・分離する能力を持たせることで、二酸化炭素の分離・回収や、排ガス中の有害物質除去、さらには空気清浄技術などへの応用ポテンシャルも高いとされています。
分子操作・ナノ空間制御の普遍的価値
北川氏の注目すべき点は、ガス吸収や貯蔵という応用面だけでなく、「空間を化学的に操作し、分子をナノスケールで制御する」という基盤的な化学の可能性を切り開いたことです。
こうした“化学空間制御”という概念は、将来的には分子ロボティクス、分子機械、ナノリアクター設計など、次世代の化学技術の土台ともなりうるものです。
加えて、構造の応答性(ソフトクリスタル性)を組み込んだ MOF は、単なる“穴あき材料”の枠を超え、物質が環境に反応して機能を変える「スマート材料」への道を拓くものでもあります。
受賞効果と今後への期待
日本化学界・若手研究者への励み
日本人研究者がノーベル化学賞を受賞することは稀であり、化学を志す学生や若手研究者にとって非常に励みになるニュースです。
研究資金支援や国際共同研究の推進にも好影響をもたらすでしょう。
さらなる発展と挑戦
受賞によって、北川氏のグループや関連分野には、素材設計、構造制御、応答性制御など多くの新しい挑戦が期待されます。
たとえば、より複雑な機能を持つ多孔性材料、あるいは複数成分ガスの同時計測・分離を可能にする材料設計などは、今後の発展の方向性になり得ます。
また、実用化・産業応用面でも、ガス貯蔵、分離、触媒、センサー応答性材料への展開が加速すると考えられます。
研究者としての思想と人柄
北川氏は、インタビューなどで自身を突き動かす原動力について、「“無用の有用性”(いわゆる「役に立たなさそうなものの中にこそヒントがある」)」という概念に共感したと語っています。
また、彼は粘り強さ、地道な探求、偶然性への洞察を重視するスタンスを大切にしており、研究とはただ新しい物を作るだけでなく、コンセプトを描き、ビジョンを持って先を予測することが鍵だと語ることが多いようです。
技術者としてだけでなく、研究者としての倫理観や姿勢も世代を超えて語り継がれるでしょう。
結びに:未来への化学的挑戦
北川進氏のノーベル化学賞受賞は、単なる栄誉にとどまらず、化学という学問そのものに新しい広がりを与えるできごとだと言えます。
多孔性金属錯体という高度な素材設計技術を通じて、「空間を化学で設計する」という発想が一般化すれば、未来の物質科学、ナノ技術、環境・エネルギー分野さらには医療応用さえ変える可能性を秘めています。
今後、この受賞を契機として、国内外での研究投資や人材育成がさらに進み、より高度で実用性ある“空間制御材料”の世代交代が進むことを、多くの化学ファン・技術者として期待したいところです。
|
|
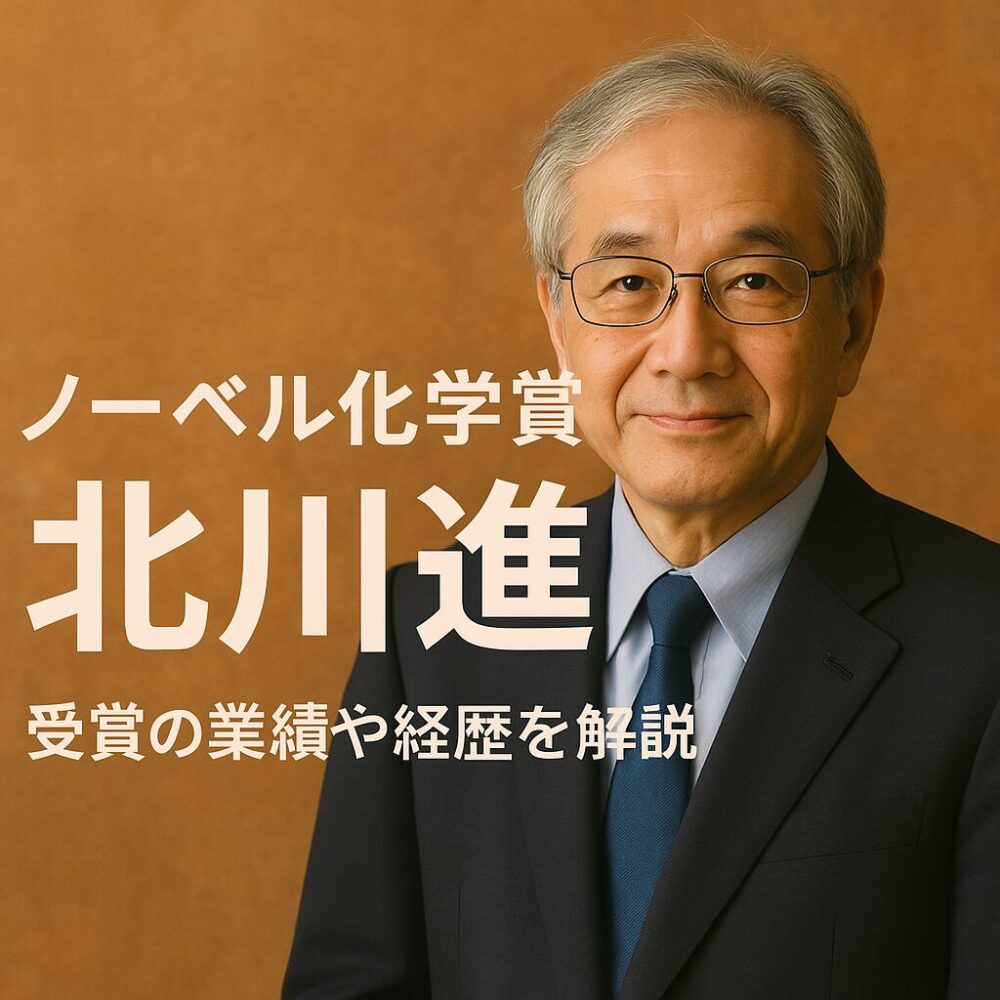
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d31da72.a42232c0.4d31da73.8e05632d/?me_id=1213310&item_id=20731307&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7063%2F9784860647063_1_6.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


